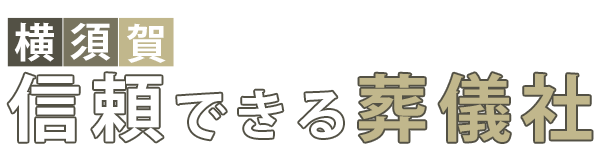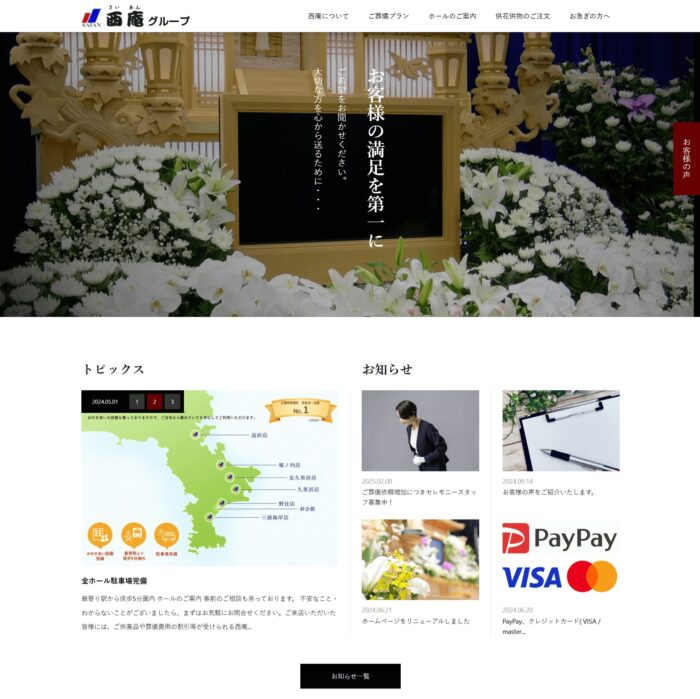近年、家族葬が増えたことにより、葬儀に参列する機会は減少しています。しかし、葬儀は予期せぬタイミングで行われるため、事前にマナーを把握しておくことはとても重要です。本記事では、葬儀に参列する際に知っておきたい基本的なマナーやお焼香、供花などについて詳しく解説します。
葬儀前に押さえておきたい基本マナー
葬儀は予期せぬタイミングで行われることが多いため、事前にマナーを知っておくと、安心して参列できます。
ここでは、葬儀に参列する際に押さえておきたい基本的なマナーを紹介します。
服装について
葬儀では、喪主や参列者としての役割に応じた服装が求められます。
喪主や第3親等の親族であれば、和装の紋付羽織袴を着用するのが一般的です。
洋装の場合は、モーニングコートが適切とされています。参列者の場合、男性はブラックスーツを着用しましょう。女性の場合、和装なら黒地の紋付に袋帯か名古屋帯を着るのが一般的で、洋装なら黒のワンピースやアンサンブルが好まれます。
供物や供花のマナーについて
親族や友人として葬儀に参列する際、供物や供花を送ることがよくあります。
供物や供花を送った場合、香典を包む必要は基本的にありませんが、親しい間柄であれば香典を送ってもマナー違反にはなりません。供物としては果物や海苔が一般的で、地域によっては価格帯に差があることがあります。また、贈り物には不祝儀の水引を掛けることがマナーとされています。
香典のマナーについて
香典の表書きは宗派によって異なりますが、一般的には「御香典」や「ご霊前」といった表書きを使います。
水引の下に名前を記入します。連名で香典を送る場合、3名まで名前を記載できますが、4名以上になると「○○一同」と記入するため、その点に注意が必要です。香典を記入する際は、薄墨で書くのが好ましいとされていますが、うまく書けない場合は中袋にペンで記入しても問題ありません。
お焼香と供花の正しいマナー
お焼香や供花は葬儀における重要な儀式であり、それぞれに正しいマナーがあります。
とくにお焼香は宗派によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。ここでは、お焼香と供花の正しいマナーについて詳しくご紹介します。
お焼香のマナーについて
お焼香を行う際、まず数珠を左手に掛けます。
お焼香の作法は地域や宗派によって異なりますので、事前に確認しておくことが重要です。たとえば、日蓮宗では、お焼香の回数が1回または3回と定められており、香をつまんだ後、それを額の高さまで持ち上げる「おしいただく」という作法があります。
宗派による違いがあるため、事前にどの宗派の儀式かを把握し、適切に行動することが求められます。
供花に対するマナー
供花を送る場合、葬儀・告別式の前日までに届けるのが一般的なマナーです。
しかし、近年ではご遺族の意向で供花や香典を辞退する場合も増えてきています。供花を送る前に、遺族が供花を受け取る意向があるかどうか確認することがマナーとされています。事前に確認することで、無用なトラブルを避け、故人や遺族に配慮した行動ができます。
挨拶や弔辞で禁止されている言葉とは
日本の葬儀では、言葉に精霊が宿ると信じられており、言葉遣いに細心の注意が必要です。
挨拶や弔辞でよく使われる「たびたび」や「しばしば」という言葉は不適切とされ、代わりに「よく」や「いつも」と言い換えるべきです。また「忙しい」という言葉も不吉とされ「多忙」などと言い換えるように注意が必要です。葬儀の場では、適切な言葉を選ぶことが、故人や遺族への配慮を示す重要な部分です。
通夜から告別式までの流れとマナー
親族や親しい友人として葬儀に参列する際は、通夜から告別式までの流れを理解し、適切なマナーを守ることが大切です。
ここでは、通夜から告別式までの流れと、それぞれの場面でのマナーについて詳しく解説します。
通夜ふるまいに関するマナー
通夜ふるまいは、通夜の後に親族が別室で故人との最後の食事を共にする習慣です。
遺族から通夜ふるまいに招待された場合は、断らずに参加し、箸をつけるだけでも構いません。通夜ふるまいを断ることはマナー違反とされているため、できるだけ参加するようにしましょう。
しかし、遺族も疲れているため、長居せず、手短に済ませるのがマナーです。食事の場であまり多くを話さず、故人への敬意を表すよう心掛けましょう。
弔辞に関するマナー
弔辞をお願いされた場合は、断らずに引き受けるのが一般的なマナーです。
弔辞は故人を偲び、その人柄や思い出を伝える場であり、遺族への励ましの言葉も大切です。弔辞を作成する際には、悲しみや感謝の気持ちを込めて、故人の素晴らしい点を語りましょう。
また、弔辞は葬儀終了後に遺族へ引き渡されるため、丁寧に作成することが大切です。あらかじめ内容を整理し、心のこもった言葉で故人への感謝と哀悼の気持ちを表現しましょう。
出棺や拾骨のマナー
出棺は故人との最期の別れの時であり、親族や親しい友人が集まって行われます。
出棺時には、合掌か黙礼をして故人をお見送りするのがマナーです。このとき、故人に対する敬意を表す静かな態度が求められます。拾骨は、故人の遺骨を収める儀式で、通常は2人1組で行います。最初に歯の部分を拾い、その後、足元から順番に骨を納めていきます。
拾骨は交代で行うことが多く、2度または3度交代しながら進めます。また、喉仏は一番最後に拾うのが一般的です。喉仏を最後に拾うのは、仏様が座禅を組んでいる姿に似ているとされ、敬意を表する意味が込められています。喉仏を拾うのは、故人と最も縁の深い人物や喪主が行うことが多いです。
まとめ
葬儀に参列する際には、事前にマナーを理解し、故人や遺族に対する敬意を表すことが重要です。服装や香典、お焼香、供花など、それぞれの場面で求められるマナーを守ることで、心温まる参列ができます。また、通夜や告別式、弔辞の際にも配慮が必要です。葬儀の文化や儀式に敬意を払い、適切な言葉遣いや行動を心掛けることが、故人を偲び、遺族を支える大切な姿勢となります。