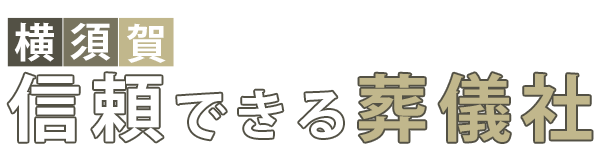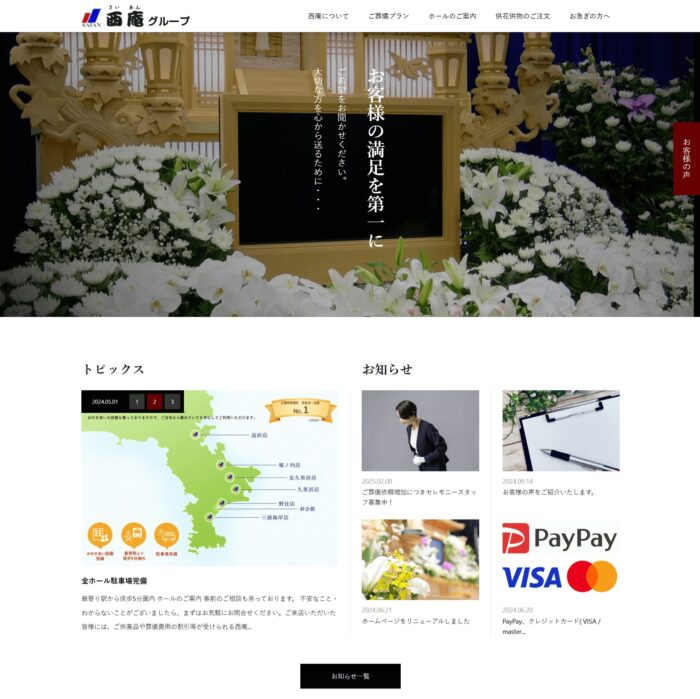突然の不幸により葬儀の準備が必要になったとき、葬儀費用を工面できるのか不安な人も多いのではないでしょうか。平均100万円以上かかるとされる葬儀費用は、急な出費としては非常に大きな負担となります。しかし、公的な支援制度や費用を抑える方法を知っておくことで、経済的な負担を減らしながら故人をしっかりと見送ることが可能です。
葬儀費用が支払えないときの対処法
葬儀費用が用意できない場合でも、制度を活用することで適切な対応が可能です。まずは支援制度を調べ、費用負担を減らす選択肢を検討することが重要です。さらに、事前の備えを行うことで、急な出費にも落ち着いて対応できるようになります。
公的制度を活用すれば自己負担を大きく抑えられる
生活に余裕がない場合でも、行政が提供する支援制度を利用すれば葬儀費用を軽減できます。生活保護を受けている場合は、葬祭扶助制度を申請することで、火葬に必要な基本的費用を公費でまかなうことが可能です。
制度では遺族だけでなく、第三者の申請も認められるケースがあるため、条件に当てはまるか自治体に確認してみましょう。また、国民健康保険加入者の葬儀には葬祭費として5万円前後の補助金が出ることもあり、手続きは葬儀後2年以内が原則です。
故人の資産や保険を確認して即時の費用に充てる
故人が遺した生命保険や預貯金をうまく活用すれば、急な出費にも対応できます。生命保険の死亡保険金は、受取人が明確であれば比較的早く支払いが行われるため、葬儀代の即時資金として活用しやすい特徴があります。
預貯金の仮払い制度を使えば、相続手続きの完了を待たずに一部資金を引き出すことが可能です。法定相続分の3分の1または150万円が上限となりますが、複数の金融機関に分かれている場合は合算できることもあります。
急な葬儀費用に困った際は、資産の存在を速やかに確認することで状況を乗り切る手段になるかもしれません。
葬儀の費用を支払えないときに利用できる支援制度
もしも葬儀費用の支払いが難しいと感じたら、支援制度の利用を前向きに検討しましょう。条件を満たせば、自治体の補助や保険金によって費用の全額、または一部をまかなうことが可能です。制度は申請期限や条件が決まっているため、早めに情報収集をすることが重要です。
生活保護受給者向けの「葬祭扶助制度」
生活保護を受けている人、または故人が生活保護受給者だった場合には、葬祭扶助制度の利用が第一の選択肢になります。遺体の搬送から火葬までの最低限の費用を自治体が負担してくれるため、遺族の自己負担は基本的にゼロです。
対象になるのは、申請者が生活保護を受けているか、故人が身寄りのない生活保護受給者だった場合などです。支給には事前申請が必要で、葬儀後に手続きをしても対象にならないため注意が必要となります。
福祉葬などの名称で呼ばれることもあり、自治体によって細かな内容は異なるので、事前に福祉課などへ問い合わせましょう。
健康保険や年金制度からの補助金も見逃さない
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主は葬祭費の支給を受けられる可能性があります。支給額はおおむね5万円前後で、申請は葬儀後2年以内に行うことが必要です。
また、厚生年金加入者や企業の健康保険に加入していた方については、勤務先を通じて埋葬料や埋葬費として給付を受けられることもあります。さらに、一定の条件を満たす国民年金加入者には死亡一時金が支給される制度もあり、金額は納付期間に応じて異なります。
葬儀費用を抑える方法と準備しておきたいこと
葬儀費用に不安がある場合は、できるだけ早い段階から準備や対策を講じることが大切です。費用を抑える選択肢は多く、小規模な葬儀や自治体支援を活用する方法があります。さらに、生前から保険や互助会に加入しておくことで、遺族の負担を大きく減らすことが可能です。
家族葬や火葬式など小規模な形式で費用を削減
一般的な葬儀と比べて、家族葬や直葬は大幅に費用を抑えられます。家族葬は近親者のみで行うため、会場規模もコンパクトで接待費も抑えることが可能です。
一方、火葬式は通夜や告別式を省いて火葬のみを行う形式で、費用は最も安く抑えられる手段として注目されています。さらに、一日葬という通夜を省略したスタイルも増えており、精神的・身体的な負担も軽減されるというメリットもあります。
保険や互助会で生前から備えておく
もしもの時に備えて、生命保険に加入しておくことで遺族が葬儀費用で困るリスクを減らせます。とくに死亡保険は、葬儀費用をまかなうために設定されることも多く、速やかに保険金が支払われることから利用しやすい仕組みです。
さらに、互助会の会員になっておくと、毎月少額を積み立てながら葬儀に必要なサービスを会員価格で受けられるというメリットがあります。
葬儀の内容や規模を事前に相談できる点も、精神的な安心につながります。家族に加入内容を共有しておくことで、いざというときもスムーズに手続きを進めることが可能です。
まとめ
葬儀費用が支払えない場合でも、複数の対処法が存在します。たとえば生活保護を受給している方は葬祭扶助制度が利用でき、自己負担なしで葬儀を行うことも可能です。また、市区町村からの葬祭費補助や生命保険の保険金、預貯金の仮払い制度などを活用すれば、急な出費にも対応できます。さらに、直葬や一日葬など費用を抑えた葬儀形式や、会員割引を用いた格安プランを選ぶことで、無理なく故人を見送る方法もあります。事前に情報を集め、準備しておくことが、精神的・経済的な負担を軽減するために重要です。